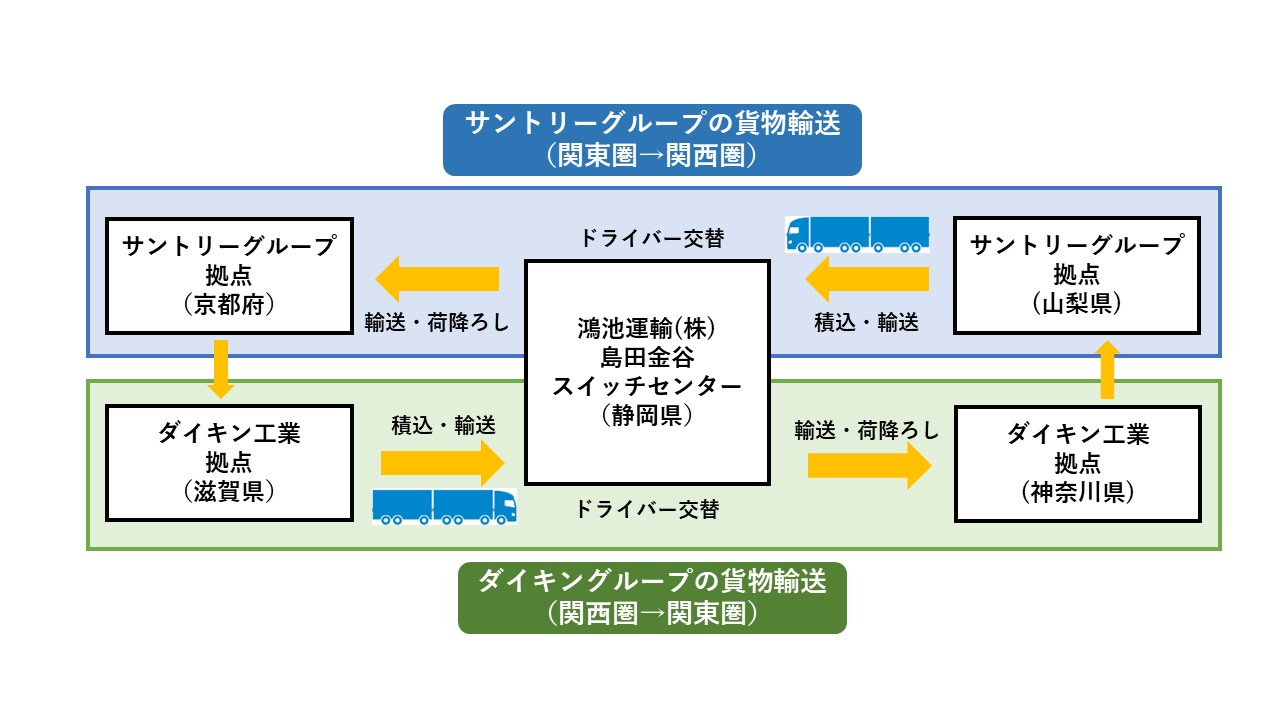お客さまの期待を超え続ける、KONOIKEのモノづくりの「改善」に迫る
当たり前のように手にする飲料製品。
その製品がつくられ、私たちの手元に届くまでには、実は多くの工程が必要となる。
空瓶に中味を注入し、ラベルを貼り、箱詰めし、確実に出荷する、この重要な役割を担っているのがKONOIKEグループだ。
例えば、栃木県にある国内大手飲料メーカー・サントリー(株) (以下、サントリー)栃木 梓の森工場では、鴻池運輸(株)(以下、鴻池運輸)が年間数百万ケースにのぼる製品の「パッケージング業務」を一手に引き受けている。サントリーホールディングスにおいて国内最大のスピリッツ・ワイン生産量を誇るこの工場で、半世紀近くにわたり、製造ラインの運転から設備保全までを支え続けてきた。
今回紹介するのは、鴻池運輸が主導した製造設備の改善プロジェクト。
20年以上解決が難しいとされてきた設備の課題を解決し、その成果は工場を運営するサントリーからも「私たちもお手本にしたい」と高く評価された。
なぜ彼らはここまでの信頼を得ることができるのか。
「期待を超える価値」を追求し続ける、鴻池運輸の現場力の真髄に迫る――
「なぜ、作業者がずっと設備の前で待機しているんだろう?」
2020年、鴻池運輸の大森辰弥サブグループリーダーがサントリー 栃木 梓の森工場の別部門から異動して最初に目にしたのは、奇妙な光景だった。デパレタイザーの前で、オペレーターが常に緊張した面持ちで待機している。「異常が出る前に即座に対応しなければ、製造ライン全体が止まってしまう。製品破損のリスクもある」。そのためオペレーターは一時も目を離せない状況が続いていた。設置から20年が経過したデパレタイザーは、1日に計20〜30分の停止が日常的に発生していた。その度に、設備調整のために階段を往復する必要があり、現場のオペレーターにとっても大きな負担となっていた。
設備の稼働率は85%程度。工場全体の目標である94%には到底及ばない。この設備停止ロスを解消しない限り、目標達成は不可能だった。「この状況はおかしい。作業者の負担をなんとしても軽減したい」と大森は強い危機感を抱いた。一方で現場では、長年この状態を「設備が古いから仕方がない」と受け入れられていた。だが、大森の中には、強い確信があった。
「設備は必ず人の手によって動かされている。改善できることは絶対にあるはずだ」
製造業務を請け負う企業は、設備メーカーから納入された仕様の範囲内で運用するのが一般的だ。設備そのものの設定まで踏み込んだ改善に着手する企業は少ない。しかし、大森は、設備そのものの仕組み自体を理解し、100%の改善を追求した。
「8割の完成度で終わらせると、数年後には残りの2割の妥協が原因でトラブルが起きる。だからこそ、やるからには一切妥協せずに、100点を目指す」。この強い決意から、大森の挑戦が始まった。
大森は、まず現状把握のためのデータ収集から始めた。しかし、その道のりは容易ではなかった。1日の製造時間は朝8時半から夜10時半まで。月に1日しかない設備停止日には他の保守作業も控えており、改善のための時間の確保も困難だった。「日中は業務がいっぱいで、オペレーターの方に話を聞く時間もなかなか取れない。過去のデータもまとまっておらず、まさにゼロからのスタートでした」と大森は当時を振り返る。
そこで大森は、たった一人で、業務終了後の時間を使って地道なデータ収集を始めた。図面と機械を徹底的に観察し、本来どのような動きをするはずなのか、理論値の検証から始めた。考えられるすべての数値を記録し、あらゆる角度から検証を重ねていく。
さらに、動画撮影による実際の現場の観察も欠かさなかった。「実際に不具合が起きた瞬間を見ないと、原因は推測の域を出ない」。カメラを設置し、録画・分析を繰り返すことで、それまで思い込んでいた原因とは異なる事実が浮かび上がってきた。
約半年におよぶデータ収集と解析の結果、デパレタイザーの本来の性能と実際の運用状況との間にある「ギャップ」が明確になってきた。それは単なる設備の劣化の問題ではなく、人の手による感覚的な調整で生まれた「ズレ」が蓄積された結果だった。
「私たちは長年、設備や包材の状態が悪いからと思い込んでいました」と大森は語る。「でも実際には、条件設定を私たち自身が徐々に崩していた。データを取って初めてそれが見えてきました」と大森は語る。
しかし、この発見は始まりに過ぎなかった。次の課題は、チーム全体をいかに巻き込んでいくか。ベテラン作業者たちの経験と勘に基づく現場の常識を、どう変えていけばいいのか。大森の挑戦は、新たなステージへと進んでいった。
「最初はベテランオペレーターの方と衝突することも多かったです。『現場のことも分かってないくせに』と、言い合いになったこともありました」と大森は振り返る。「推測だけでは、誰も動いてくれない。実際にデータをとって客観的な数字を示すことで、徐々に分かってもらえたように感じます」
そうして、図面を広げ現場で真剣に調査を続ける大森の姿を見るうちに、琴寄の心境は変化していく。「毎日のように真剣に設備と図面に向き合う姿を見て、ここまで本気で取り組んでくれる人は今までいなかったと感じました」。次第に琴寄からも、現場の作業者に「ここまでやるなら、協力しよう」と声をかけるようになった。
現場が一つになったのは、大森がたった一人でデータ収集を始めてから半年以上後のことだった。転機は、大森が不在にしていた時に訪れた。オペレーターが自主的に数値データの取得を進めてくれたのだ。「そのメモを見たときに、メンバーが自分たちで現場を変えようとしているのを感じて、本当に感動しました」と大森は振り返る。それは、現場に根付いていた「待ちの姿勢」が「自ら動く姿勢」へと変わった瞬間だった。
改善活動の成果は、明確な数字となって現れた。デパレタイザーの停止率は、2022年時点の0.55%から2023年には0.35%へと大幅に改善。これにより、1日計30分以上発生していた停止時間は、ついにゼロになった。
しかしサントリーにとって、最も価値があったのは数字以上のものだった。
「工場内には他の協力会社さんもいますが、現場を一番理解してくれているのはKONOIKEさんです」とサントリー 栃木 梓の森工場の武生技師長は評価する。「設備のことを知り尽くし、原因究明から改善まで。時には私たちも教えを請うほどです」
他社が人材育成に苦心する中、鴻池運輸では次世代のリーダーが着実に育っているという。「改善に取り組むメンバーを見ていると、すごく楽しそうなんです。人を育て、現場を良くしていく。そんな活気のある職場づくりができているのは素晴らしいことです」
2016年から工場全体で推進している「安定稼働」という目標。その中で、鴻池運輸は、単なる請負先を超え、現場改善のリーダーシップを発揮している。「私たちは鴻池運輸という会社名を背負いながら、サントリーというブランドも背負っているんです」と大森は語る。その言葉には、共にモノづくりを追求するパートナーとしての誇りが込められている。
「言われたことをやるだけではなく、自発的に動くのがプロです」と大森は続ける。「例えば資料作成を依頼された時も、その先の活用を想定して準備します。サントリーさんとの付き合いが長いからこそ、求められるものの先が読める。それが結果として後戻りの少ない仕事につながるんです」。その姿勢は、常に「期待を超える」仕事を追求するKONOIKEの社員としての信念そのものだ。
「100点満点の改善とは、単にロスゼロを達成することではありません」と大森は語る。
「10年先も誰もが問題なく動かせる仕組みこそが、本当の100点だと考えています」。
改善活動を通じて見えてきたのは、技術を核とした自律自走する組織づくりの可能性だった。大森は、この先の展望をこう語る。「機械に強い人、電気に強い人、解析に長けた人。異なる強みを持ったメンバーが、お互いに高め合える環境を作りたい」。
工場の自動化が進む中、単純な設備オペレーションの需要は減少するかもしれない。しかし、機械を理解し、維持管理できる人材の重要性は、むしろ高まっていく。設備のメンテナンスも含め、すべてを内製化できるようになれば、それは鴻池運輸の大きな強みとなるはずだ。
「『自分たちの設備は自分たちで直す』。その技術を評価していただき、新しい価値提供につなげていきたい」。大森たちは次なる構想を描いている。